今回に限っては是非本編を御覧下さい。問題の本質(複数の視座の複合からなる生態学的思考)が掴めます。

神宮外苑の再開発をこのまま進めてよいのか(石川幹子東京大学名誉教授) -マル激
カテゴリー「2020年東京オリンピック・パラリンピック」「環境」 この季節、神宮外苑絵画館前のイチョウ並木には多くの人が訪れ、黄色く色づいた樹木の下で散策を楽しむ。この光景が今後も続くか、今、瀬戸際にたたされている。 神宮外苑の再開発は、2020東京五輪のために建設された新国立競技場(今は、新がとれて「国立競技場」と...
******************
建築家の槙文彦氏による建築雑誌上での問題提起を受け、新国立競技場建設案の出鱈目ぶりを、槙文彦氏を含む建築家3名と社会学者宮台の計四名が登壇して、問題の神宮外苑にある日本青年館中ホールで議論したのが2013年10月のこと。

新国立競技場を問うシンポ、槇氏の問題提起受け10月11日に〈追加情報あり〉
「濃密な歴史を持つ風致地区に何故このような巨大な施設をつくらなければならないのか」──。建築家の槇文彦氏が日本建築家協会(JIA)の会報「JIA MAGAZINE 295号(8月号)」に寄稿した文章が話題を呼んでいる。国立競技場に隣接する東京体育館の設計者である槇氏が新国立競技場の国際コンペに参加しなかった理由や、施設...
そこでの宮台の論点(2013年時点)は5つ。
①民主主義の手続きを実質的にスキップしている。
②建設案は高さ規制撤廃による地価高騰での「濡れ手に粟」が狙い。
③高さ規制撤廃は外苑の心地よさを支える歩行スケールを壊す。
④経済から見た空間space=機能の視座から、歩行者から見た場所place=体験の視座へ。
⑤[内苑=力の湧出口=聖]vs[外苑=その力に与る場所place=俗]の象徴聯関を壊すべからず。
******************
論点①と④をフィーチャした東京新聞での宮台の論説は、以下参照。
URBANING.ORG » 宮台真司が新国立競技場について東京新聞に寄稿した記事の全文
全ての論点を全面展開した宮台の著作は、以下を参照。

まちづくりの哲学:都市計画が語らなかった「場所」と「世界」
まちづくりを問うことは、私たちがなぜ生きているかを問うことだ。なぜなら、まちは「世界は生きるに値するか?」という問いの参照先だからだ。 私たちは幸福になれないことが約束されているにもかかわらず、なぜ明日もう一日生きてみようと考えるのか?私たちはただ一つの生きる動機付けである希望をまちから与えられることでかろうじて生きて...
それを踏まえて一部をアップデートした宮台の著作は、以下を参照。
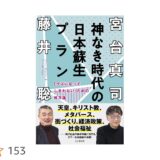
神なき時代の日本蘇生プラン
損得マシーン、自己保身に走る劣化した日本人。
ニヒリズムを潰し、社会の理を取り戻すには。
――現代社会の根本問題に対する、タブーなき議論が満載!
コロナ禍で、「仲間が消えた社会、人間の叡智が湧き出ない社会。システム化・画一化で危機に脆弱な社会」という“日本の弱み"をさんざん見せつけられた状況だ。
...



